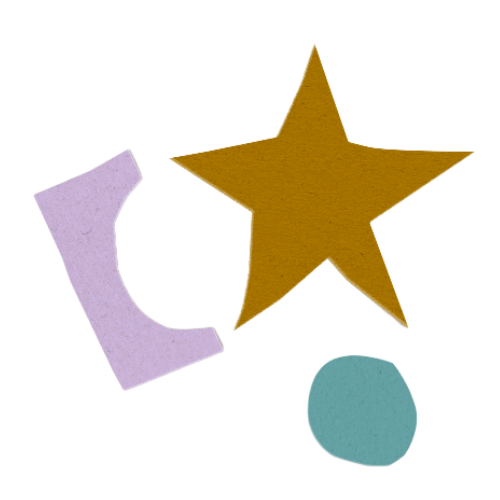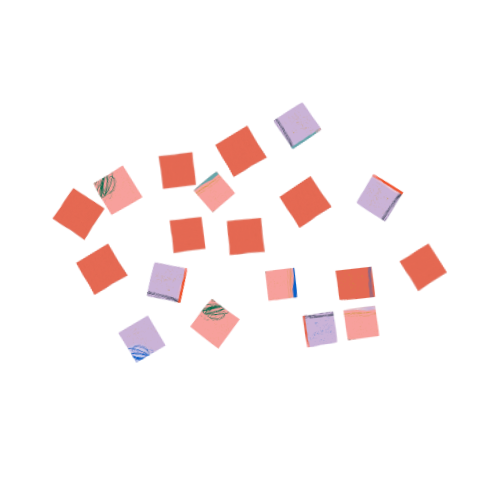Editor’s Note
作品には、そんな力があるのではないでしょうか。
本稿は、小阿瀬達基さんによる作品紹介をお届けします。
そのキスをしてはならない──戸桝有馬『螺鈿の楼閣』について
小阿瀬達基
1.
ある人が、別のある人を好きになること。この出会いは単なる偶然に過ぎないと知りながら、きっと必然なのだと己を錯覚させてゆく──けれど、その先に幸せが待つとは限らない。「やっぱり出会わなければ良かった」と胸を痛めることも少なくないだろう。叶わないと知っていた恋が終わったとき、「それでも好きになっちゃったからね」と慰めてくれるのが私自身の他にいないことは寂しい。*1
『螺鈿の楼閣』(作:戸枡有馬)は、そんな約束された失恋へ向かう物語だ。「となりのヤングジャンプ」に特別掲載された短編読み切りで、現在も公開中だ。まずは実際に読んでみて欲しい。

デフォルメされたクラゲやウサギのデザイン、あやとり、折り紙、水族館のイルカ……かわいいものが好きな男の子・主税(チカ)と、彼の友人の姉・華子。二人の距離が急接近し、きっと物語のあとには離れるばかりだろう、という予感を残して本作は幕を閉じる。
学校指定の裁縫カタログを友人と眺め、どのデザインを選ぶか話している様子を見るに、チカは10歳か11歳だろう。もうすぐ大学卒業を控えた華子とは、おそらく一回りほどの年齢差がある。
周囲に趣味や願望を言えずに過ごしてきた、引っ込み思案なチカ。しかし、華子にだけは正直な思いを語るようになっていく。華子もまた、自分にはふさわしくないと諦めつつあった教師の夢をチカに明かし、「……これ 誰にも言えなかったの」と呟く。
年齢も立場も異なる二人は、互いに唯一心を許す相手となった──そして、それぞれが「ある告白」を決断する。
2.
「俺 華子さんのことが好きです」「だから これからもずっと一緒にいてっ」「それでっ 大人になったら 俺と…」
「ずっとは 無理だよ」「だって わたし…」「…」「言ったでしょ?わたしは」
「“子供”が好きなの」
戸桝有馬『螺鈿の楼閣』45-47頁
ずっと一緒にいたい、と想いを告げるチカ。そんな彼に、華子は自身がペドフィリア(小児性愛者)であることを明かす。「ずっと一緒に」いれば、チカは大人になってしまうし、そうなれば彼を好きではいられない。そう語る華子に、チカは「大人になったら 嫌いになっていいよ」と訴え、彼女の涙をぬぐう。
思わずその手を取り、チカに覆いかぶさるように身を寄せる華子。彼女が「大人になったら 俺と…」の続きを尋ねると、チカは「わかんない… ただ 好きだから ずっと一緒にいたかっただけ」と答える。
華子はその答えにショックを受ける。「大人になったら 何がしたかったの?」と問うたとき、彼女はその答えに「大人」らしい欲求──身体に触れたい、触れられたい、という性的な期待──が含まれていることを少なからず予期していたからだ。「子供」しか好きになれない「大人」である華子自身、チカへのそうした欲求に苛まれ、抗っている。
しかし、チカは違う。彼が望むのは、好きな相手と(たとえ「大人」になっても)ただずっと一緒にいることだけだ。それを告げられたとき、華子は「大人」と「子供」の決定的な差異を思い知らされ、同時に「子供」という存在にあらためて惹かれたのではないか。彼女にとって大人とは、「つまらないことばかり考える」──すなわち、好きな人と「ただ一緒にいる」だけでは満足できず、性的な視線を向け、その先に手を伸ばして触れたい、触れられたいと考えてしまう存在だ。*2 華子にとって、それはきっと人並み以上に耐え難く理不尽な業のように感じられるのではないか。
ペドフィリアがセクシャルマイノリティのなかでもとりわけ苛烈な非難を受けるのは、まさにそうした理由だ。小児性愛は、ときに児童への性的欲求をともなう。それが行動に移された場合、児童の深刻な精神的ダメージや、のちの人生に大きな影響を与えるようなトラウマを生みかねない。そのため、当事者はしばしば「犯罪者予備軍」という強固なレッテルが貼られ、また自らもそれを強く意識していることが少なくない。
だからこそ、華子もまた教職という進路をためらい、「(自分がチカのことを)好きじゃなければいいのに」と涙ながらに語る。彼女の「チカが好き」という気持ちは「チカに触れたい、触れられたい」という欲求と切り離すことができないからだ。「華子が好き」というチカの言葉が、同じ意味の欲望を含まないであろうこととは対照的に。
3.
仮に、チカの答えにそうした「大人」らしさが含まれていたとしたら。華子は落胆と寂しさを覚えつつも、「子供だが、すこし大人になりつつある」チカにキスをしていたかもしれない。けれども、チカの答えは違った。それを聞いた華子は、繋いだ手と、いまにも唇が触れそうな距離まで近づけた顔を離し、放心と驚きが入り交じったような表情を浮かべる。̇そのとき、彼女は「私も、こうなりたいのだ」と痛感していたのではないか。
私もチカのように、ただ好きな人と一緒にいるだけで満足したい。今だけでも、そうなれたら……華子がキスをしなかったのは、そんな思いがよぎったからではないか。たとえ本当は触れたいと願っていたとしても、ここでキスさえしなければ。いまだけは「子供」のように、他者を愛せたことになる。*3
仮に、ペドフィリアであることが尊重される社会になったとしよう。それでも、華子の望みが完全に叶うことはないはずだ。彼女は単に「子供が好き」なのではなく、「大人」としての自分から解放され、「子供のようになりたい」という羨望を抱え込んでいるのだから。
たしかに、子供は羨ましい。もし、とうに大人になった私が「好きな人と一緒にいられさえすれば、もうそれだけで良い」と言ったとする。おそらく、それは信じてもらえない。大多数の人から「いや、好きならセックスとかもしたいでしょ。大人なんだし」と思われるはずだ。けれど、チカなら信じてもらえる。まだ髭も生えず、声変わりも迎えていない「子供」だからだ。しかし数年後、16歳になった彼が友人に同じことを語れば、きっと「恥ずかしがんなって」「お前、勃たねぇの?w」といった反応が返ってくるだろう。
恋愛感情と性欲は、セットであることが前提とされる。*4 前者を向けた相手には、後者もまた向けることが当然だと考えられている。繰り返すが、仮に私が「好きな相手とキスやセックスをしなくても別に良い。一緒にいられたら、それだけで良い」と言ったとしても、ウソかウケ狙いだと思われるか、あるいは「じゃあそこまで好きじゃないんだね」と理解されるだろう。私は「大人」だからだ。チカとは違って、その言葉を信じてもらえる立場にはない。
それに、きっと私自身も、その言葉を完全に信じることはできない。恋愛感情と性欲が自明に結びつけられた世界に生まれ育ってきたのは、私も同じなのだから。いくら「それで満足できるんだ!」と唱えてみても「違うだろ、そう思いたいだけだろ」という反論が浮かんでくるばかりで、結論に辿り着くことはない。だからこそ、なんのためらいもなく「一緒にいるだけで良い」と、心から口にできるチカはまばゆい。
華子もまた、その光に焼かれていたはずだ。「たしかに私は子供が好きだ。でも、一緒にいるだけで満足できる」と唱えては、「違うだろ、そう思いたいだけだろ」と自嘲してきたであろう彼女にとって、その迷いなさは羨望に値する。こうなれたら、どんなに良いか。ただ、子供のそばにいるだけで十分に満たされるなら。あなたと出会えて良かったと、心の底から言えるのに。なぜ、私はあなたのようになれないのだろう。
そしてなぜ、あなたもまた、いずれ私のようになってしまうのだろう。
あなたと私が「一緒」であること──それは、この物語において繰り返し描かれていたモチーフでもある。華子の服を借り、彼女の匂いをまとうチカ。一本のリップを使い、実際には許されることのないキスを疑似的に交わす華子。二人とも孤独で、かわいいものに惹かれ、そして「好き」を隠している。二人が「一緒」を見つけるたび、別れに近づく。
そしてチカは、「好きだから、ずっと一緒にいたい」と告げる。これからも決して離れることなく、共に生きていきたい。時間を、場所を、気持ちをずっと一緒にできたら幸せなのに。けれど、その望みは彼一人のものだ。華子は好きな相手と一緒にいるだけでは満たされないし、大人になってしまったチカを好きではいられない。
だから──ずっとじゃないけど、今は好き。二人の「好き」は、そのようにしてしか、叶わない。
*1 友達ってこういうとき、だいたい「だから言ったのに」とか「次行こ!」などと言う。
*2 大人には自他境界がはっきりとあるが、子供にはそれが希薄だ、とも言い換えられそう。「私とあなた」の境が曖昧になるような愛情を、身体的に繋がりを持たずには実感できない大人と、そんなものがなくとも「一緒」になれる子供。
*3 まぁ、ハグはしたんですけどね。
*4 「交際願望」もまた、恋愛感情と強く結びつくものだとされている。「好きだけど、付き合えなくても良い。セックスも、別にしなくたって良い」……そのような主張を信じてもらえる存在がいるとすれば、やはりそれは子供だけだろう。また、仮に大人がそうした主張を信じてもらえたとしても、それは「未成熟だ」とみなされることを免れないだろう。